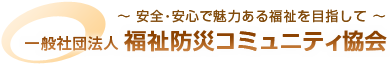2024年12月4日(水曜)
独立行政法人福祉医療機構(WAM)様で2023年10月11日から2024年10月30日にかけて配信した「業務継続計画(BCP)対策セミナー」、【理論編】には2,591名、【災害対応編】には1,789名と、延べ4,000名以上にご視聴いただきました。
受講者の方々は、社会福祉法人の役員、施設長、職員をはじめ、福祉・医療関係者や行政、防災士、企業関係者など、幅広い分野からご参加いただいています。
多様な視点と現場の声が詰まった感想の中から、一部ではございますが、皆様にご紹介させていただきます。ぜひご覧ください。
【理論編】
- 福祉施設がBCPを作成することがなぜ重要なのか、理論を知ることができ、BCPを事業所で作成する根底の部分を理解できました。
- 人間は正常化の偏見があり、備えたり逃げたりするのが苦手な生き物であるという先生の言葉に、なるほどと思いました。様々な災害を見聞きしたり、自身も体験したりしているにも関わらず、準備がしっかり出来ているかと言えば出来ていません。様々な被害状況を考え、対策を考えていくことが大切だと思いました。
- 安全だという「偏見」(自分は、自施設は・・・)がいかに想像力を阻んでいたか、とても大きなことでした。その視点で話を聞いていくとよくわかる素晴らしい講義でした。
- 正常化の偏見という言葉に深く考えさせられました。利用者さんや高齢者の命、くらし、尊厳を守れるのは私たちで、しっかりできる対策をしていこうと感じました。先生の話し方もとても分かりやすく、秋田弁が心落ち着くしゃべり口調でした。
- 正常化の偏見など、とても心に残る言葉をいただくとともに、BCPの重要性を再認識できました。
- 正常バイアスで日頃過ごしていることに気づかされました。パート職員という立場で、職場では受動的な立場にいると考えていたけれど、今後もっと積極的に万が一、いざ、について考えて取り組んでいきたいと思いました。
- BCPの作成意義を確認することができました。計画の見直し、課題抽出の参考になり、職員の研修を実施することができました。
- 鍵屋先生のお話がとてもわかりやすく、しかも実践的でした。
- BCPの重要性を、職員たちへ伝える要素が多くありました。
- BCPの必要性が分かり、どう作りたいかを考えることができました。
- 何が大切か、何を優先するか、わかりやすくご説明くださった。日常業務を振り返る契機ともなりうると感じました。
- BCPに関してはガイドラインに沿いながら作成してもこれで良いとなかなか思えず、頭を悩まし続けていますが、最初から完璧に仕上がるものではないと知りました。業務を継続するためにライフラインの確保をはじめ初動体制や職員の参集、災害を最小限にするための設備的な準備など、施設の職員はじめ、地域の方々とのつながりも大切にしながら訓練を実施し、修正を繰り返していこうと思います。
- 事業継続の必要性が、事例を踏まえた中で分かりやすく明確に語られ、理解が進みました。秋田弁のお話も楽しかったです。
- 被災地に赴いて調査しているところに説得力を感じ、とても現実的な内容だと思いました。
- わかりやすく、優しい言葉での講義が良かったです。出来ているBCPを見直すきっかけになりました。
- 資料や統計に基づき説明して下さったので、説得力があり、分かりやすかった。
- BCPについて、漠然としか理解できていなかったので、今回を機に理解することが出来ました。
- 非常食の3日分の献立を表示することが大変参考になりました。非常食の個数、賞味期限は書いていますが、いざ渡すときに忙しくてうまく配布できないと感じています。こうした課題をしっかり施設全体で取り組みたいと思います。
- 在宅の被災者支援も重要ということがわかり、我々在宅の介護支援専門員の優先すべき課題が明確になりました。
- 福祉事業所が出来るだけ損失を少なくし、事業の継続・再開を様々な機関と連携して早期に実施することが、利用者だけでなく地域の福祉を守るということに改めて気づかされました。
- 福祉施設職員として、施設内のみの安全を確保するだけでなく、地域全体のことも含めてBCP計画の策定及び防災意識を持つことが重要であると気づくことができました。
- 障害のある方や高齢の方の災害時の実情を改めて考えさせられ、まだ理解が足りない事にも気づいた。BCPの必要性が理解できました。
- BCPを見直さなければと個人的に思っても、行き詰まり、負担感を感じていました。職場内で「なぜ必要で、何を意識して見直すか」を話し合うための足掛かりになると感じました。
- 先生の秋田弁でのお話は、大変親しみやすく、難しく感じずに学べました。
【災害対応編】
- 現在BCPを進めているため、役に立ちました。既存の計画を参考に作成を検討していたが、職員たちの意見を出し合い法人の地域に合った計画を作りたい。
- 福祉施設がなぜBCPが必要なのか、具体的にどう取り組むとよいのか、とても分かりやすく、丁寧に説明されていました。
- 防災BOXはとても良いと思いました。保育園の災害時対策向けもあると良いなと思いました。
- 介護・障害福祉施設での対応が中心になっていましたが、保育施設でも活用できる部分がありました。
- 災害時に防災BOXをまず開けるように、BCP作りのためには鍵屋先生の話を聞こう、となります。自分の施設ではどうだろうか、と考えながら話を聞くことができました。具体的に順を追っての話だったので、作成の手順もイメージできました。
- 今準備しなければならないことを再確認することができました。
- 平時からの備えが重要であることがよくわかりました。
- 福祉避難所のマニュアルについて とても参考になりました。他の話もとても分かりやすく、楽しんで聞くことができました。
- 大切なポイントを、楽しい語り口で大変わかりやすく教えていただきました。
- いつ自然災害に遭遇するかわからないため、平常時の準備と訓練が必要であると改めて理解しました。また地域との関係をつくることも大切であると思いました。
- BCPは計画を立てるだけではなく、実施して反省して見直しをしなければならない。指定福祉避難所に指定されているので、マニュアルの見直しをする必要性を感じました。
- 今まで震災の様子をテレビなどで見たことはあっても、福祉分野に特化した映像は見たことがなかったため、非常に有意義でした。
- 自身の危機意識の乏しさに気付くことが出来ました。我が事と捉え、考えたいです。事業所でBCP策定のためのグループワークや検討会があれば参加したいと思います。鍵屋教授のお話は非常に聴きやすく、内容もとても良かったです。
- 人作りや職場のコミュニケーション作りの大事さを改めて思い知らされました。それがなければBCP計画は絵に描いた餅になってしまうし、BCP計画の改善もできないということが理解できました。